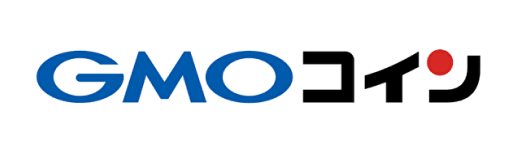- 仮想通貨で利確した時点で課税対象
- 節税が利益獲得の肝になる
- 経理を楽にするアプリをご紹介
仮想通貨は2017年に大流行し、多くの人がその存在を既に知っているという状況です。しかし仮想通貨を使って利用していても、その後の税金の問題についてあまり知ってる人がいません。今回はそんな仮想通貨の税金はどうなっているのか。どういった計算すればよいのかを紹介します。
仮想通貨に税金はかかるのか
税金はかかる
仮想通貨による利益は税金の対象となり、この所得は「雑所得」に分類されます。仮想通貨で取引で得た利益は総合課税の対象となります。
税率はどのくらいか
仮想通貨は税法上では「雑所得」に分類されるようになっており、為替差益と同様に総合課税の対象となっています。総合課税の対象であるため、給与所得などほかの収入と合算した結果に応じて、その税率は変わってきます。最大税率は45%となっており、利益が多額になればその結果、税率も比例します。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除金額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円以上、330万円以下 | 10% | 97500円 |
| 330万円以上、695万円以下 | 20% | 237500円 |
| 695万円以上、900万円以下 | 23% | 636000円 |
| 900万円以上、1800万円以下 | 33% | 1536000円 |
| 1800万円以上、4000万円以下 | 40% | 2796000円 |
| 4000万円以上 | 45% | 4796000円 |
課税義務が発生するタイミング税率はこのようになっており、仮想通貨を利用して稼いだ人は自分の所得を計算して納税額を残しておかなければいけません。基本的に仮想通貨を利用している上で課税の義務が発生するのは利益が確定した時です。
例えば、1ビットコイン1,000,000円で買っておいた際に、後日1,500,000円まで値上がりした際に1ビットコインを売却すると500,000円の利益が確定します。この時、500,000円分の利益が確定しているため、当然日本円の利益として扱われるため課税義務が発生します。
これはものを買った時でも同じです。最近ではビットコインで商品を購入すると言うサービスも出てきています。ビットコインでものを購入したとしてもそのお店自体は現金を受け取っているわけであり、仮想通貨で決済すると言う事はその時のレートで間接的に現金化しているということになります。そのため、ものを買った時も同様に課税義務が発生します。
確定申告は必要か?
仮想通貨の確定申告は必要な人と必要でない人がいます。まず大前提として仮想通貨を所持しているだけでは確定申告の必要はありません。確定申告が必要なケースとしては、利益の確定や商品を購入する、他の仮想通貨に変換するということで初めて仮想通貨の確定申告の必要性が出てきます。
会社等で労働しており、給与所得を得ている方は1年に200,000円以上の利益が出たら確定申告が必要となります。学生や主婦等で仮想家族の扶養に入っていると言う形は利益が330,000円を超えた場合は確定申告が必要となります。フリーランス、個人事業主の方々は利益の額がどんな額であっても確定申告が必要となります。
仮想通貨の税金の計算方法
実際、先ほどのの表をもとに、計算式に当ててみましょう。
給与が400万円、仮想通貨をもとに得た利益が100万円の場合は、適応される税率は20%となっているため、
500万円×20%-427,500円
となります。これを計算すると、572500円となります。これが払わなければいけない税金となります。
たった100万円を儲けただけでここまでの額になってしまいます。
仮想通貨同士の損益通算はできるのか
そもそも仮想通貨が含まれる雑所得はその損益通算できない扱いとなっています。損益通算が可能な所得は通常、不動産、山林、譲渡所得の4種類となっています。それ以外の6種類の所得は損益通算できないと言うものになっています。
理由としてはそもそもが損失が発生する可能性の低いと言うことです。そもそも、他の所得である利子所得、給与所得、一時所得なども、発生する機会などがそこまで多くは無いため、制度を創設しても実益が薄いので、損益通算は認められておりません。
また、雑所得の性質で言えば、所得の発生が偶発的なものであるケースが多いと言うことです。副業で少し稼いだという少数のお金も雑所得に入ってしまうため、ストックとしてカウントしにくいと言う部分もあります。
要するに、あまり本気で稼ごうとしていない趣味に関係する支出などを雑所得の経費として認めてしまい、結果として損失が出てしまった場合、生活費に弊害が出るリスクがあります。
仮想通貨利益を節税するポイント
仮想通貨に税金が重くのしかかることはご理解いただけたと思います。しかし、いくつかの仮想通貨で得た利益の節税のポイントがあるので紹介します。
ふるさと納税を利用する
ふるさと納税は100,000円寄付すると確定申告をした際に9万8000円相当の税金減免されます。もちろん、限度額があるので無限にできるわけではありませんが、少しでも負担を和らげることができます。
個人事業主になる
次に個人事業主として登録することによって、経費を計上しやすくなり、節税対策しやすくなります。個人事業主になると確定申告の際に白色申告と青色申告があります。帳簿の作成を行いながら必要経費を控除できるとされている白色申告と、青色申告にすると仮想通貨で得ていた利益は雑所得ではなく、事業所得扱いとなります。青色申告の場合は利益から650,000円の控除が認められます。
仮想通貨税金計算ができるサービス4選
仮想通貨の流行に乗じて、仮想通貨の税金計算のサービスが普及されていきました。大変便利で、ものによっては税理士のサポートなどもついているため、個人事業主の人にも便利なものになっています。
Guardian
Guardianは「仮想通貨税務」専門の税理士さんを紹介し、複雑な税金計算や確定申告書の作成をフルサポートしてくれるサービスです。
国内のほとんどの取引所について対応している上、メディアにも多数紹介されており高い信頼性を備えていると考えて良いでしょう。
他のサービスと比べて、ユーザーにとって非常に手厚いサービスが期待できますので「かそ部」オススメのサービスです。
freee
まずクラウド会計サービス等でとても有名な「freee」です。「freee」では取引履歴データから支出を計算してくれたり、個人事業主の方には確定申告の書類の制作も可能となっています。機能の豊富な有料版と無料版があります。
CryptoLinc
次にクリプトリンクです。こちらは今年の2月にリリースされたサービスで仮想通貨投資を行っている税理士達が仮想通貨の確定申告サポートや収支の計算システムを開発しました。作成した資料などもそのまま税理士に渡すことで確定申告がスムーズに終わります。
coin tool
今年の2月にリリースされたサービスで、クラウドファンディングを利用して成立したサービスとなっています。国内の取引所に対応しているため、日本国内で使うには不自由がありません。税理士によるサポートもついているため、安心して利用することができます。
仮想通貨利益計算のできるアプリ3選
同じように仮想通貨の利益を計算できるサービスも続々と出てきています。これから先も多くのアプリが出ますが、現在出ているアプリを紹介します。
G-tax
国内の仮想通貨取引所を網羅している損益計算サービスです。新しいサービスを常に生み出し続けており、これからも進化を続ける損益計算サービスとなっています。運営する会社が「Guardian」という会社で、今勢いのある企業です。
tax@cryptact
無料で提供されている損益計算アプリです。手数料計算や明細が出せるなど、個人事業主にとっては嬉しいサービスが盛りだくさんのアプリとなっています。対応可能な取引所も多いため、利用している人も多いです。
Keiry
「Keiry」は無料で提供されている損益計算サービスです。取引所と連携することでとりき記録や残高を取り込んで、自動で計算してくれます。また、個別で対応できるように問い合わせフォームがあるのも魅力です。
まとめ
今回は仮想通貨で得た利益の計算方法を紹介しましたが、仮想通貨にはどうしてもこういった経理が関わってしまい、事務作業を億劫に感じている人もいるのではないでしょうか。そんな人のためにも便利なサービスやアプリがたくさんでているため、うまく使いこなして経理の時間を節約することも仮想通貨を運用するうえで必要なことです。