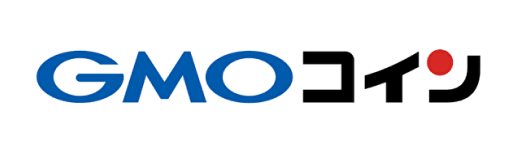- 仮想通貨の利益は「雑所得」
- 発生した利益は確定申告が必要
- しっかり節税をしましょう
仮想通貨でも利益が出れば、当然納税の義務が発生します。
本記事では、仮想通貨に関する所得と納税の仕組みについて、徹底解説します。仮想通貨取引で発生する税金についてポイントを押さえ、しっかり節税に取り組みましょう。
税法上の仮想通貨取引
確定申告は同じ年の1月1日から12月31日までが対象となり、翌年の2月16日から3月15日までの間に各地の税務署で行われます。
利益が発生した場合は、確定申告によって納税を行います。サラリーマンの場合は年末調整がありますが、給与以外の所得がある場合や個人事業主の場合などは、それとは別に確定申告を行わなければなりません。
ただし金額によっては納税の必要がなく、確定申告も不要になるケースもあります。
仮想通貨取引で得た利益は雑所得
所得にはいくつかの区分があります。例えばサラリーマンが得る給与は「給与所得」、不動産に関する所得は「不動産所得」など、全ての所得は10の区分のどれかにあてはまります。
仮想通貨に関する所得は「雑所得」に該当します。株式の所得は「配当所得」になりますが、それらの金融商品とは区分が異なるので注意が必要です。
ちなみに「配当所得」の場合は「繰越控除」という制度があり、赤字になった年は翌年の黒字分から差し引きできるという優遇措置を受けることができます。
しかし「雑所得」の場合は繰越控除が適用されず、赤字分を翌年に繰り越すことはできません。
仮想通貨の利益の計算方法
仮想通貨の所得とは、利益から損失を引いたものです。1月1日から12月31日の1年間に500万円のプラスがあっても、同じ期間に300万円のマイナスがあれば、仮想通貨の所得額は200万円です。
注意しなければいけないのは、どのタイミングの金額を計算するかということです。結論から言うと、「利益または損失が確定したタイミング」です。仮想通貨のまま保有していた場合は、所得計算の対象外です。そのため含み益や含み損がどれだけ大きな金額になっていても、仮想通貨のまま保有している限り、税金が絡んでくることはありません。
仮想通貨で購入
また仮想通貨で直接買い物をした場合も確定したとみなされます。買ったものの日本円の金額で、損益が計算されます。
1BTC=10万円のときに1BTC購入し、1BTC=15万円のときに1BTCでパソコンを購入すると、15万円-10万円=5万円の利益と計算されます。
マイニングやエアドロップで取得した通貨
マイニングやエアドロップで取得した通貨は、取得費0円として計算されるため、売却額がそのまま利益として計算されます。
仮想通貨間の取引
仮想通貨の所得計算で最もややこしいのが、仮想通貨と仮想通貨の取引です。日本円にしていなくても、取り引きのタイミングの日本円での時価総額で、損益の計算が必要です。
しかし、仮想通貨の確定申告には便利なサイトやソフトもいくつか開発されてます。取引所から取引記録をダウンロードし、そのデータをもとに自動計算してくれるものもあります。全ての計算を自分でするのは大変ですが、便利なサイトやソフトを利用して、できるだけ簡単に行いましょう。
確定申告が必要なケース
雑所得がマイナスであれば、確定申告は不要です。ただし、他の所得があれば確定申告が必要な場合もあります。配当所得で、翌年に繰越控除の適用を受けたい場合も確定申告が必要です。
また雑所得がプラスの場合でも、確定申告が不要となる場合もあります。確定申告が必要となるのは、次の3つのいずれかに該当する場合です。
- 給与所得を得ており、1年に20万円以上の利益が発生した場合
- 家族の扶養に入っており、1年に33万円以上の利益が発生した場合
- フリーランス、個人事業主の場合
納める税金はどのくらい?
仮想通貨の利益が「雑所得」になることは上記の通りですが、雑所得は総合課税の対象です。仮想通貨関係以外の所得がある場合、合算した金額で税率が決まります。
そのため仮想通貨での所得があれば、給与所得の税率も変わる可能性があります。給与所得の税率が変わると、その差額も納税しなければなりません。
課税される所得金額と税率は、以下の通りです。
| 所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え、330万円以下 | 10% | 97500円 |
| 330万円を超え、695万円以下 | 20% | 427500円 |
| 695万円を超え、900万円以下 | 23% | 636000円 |
| 900万円を超え、1800万円以下 | 33% | 1536000円 |
| 1800万円を超え、4000万円以下 | 40% | 2796000円 |
| 4000万円超 | 45% | 4796000円 |
(住民税10%が、さらに加算されます)
給与所得が600万円の場合の税率は20%ですが、仮想通貨による雑所得が200万円あると合計所得は800万円になり、税率は23%になります。この税率は雑所得だけでなく、給与所得にも適用されます。
上記の場合、雑所得がないときの税金は、
600万円 × 20% ー 427,500円 = 772,500円雑所得があるときの税金は、
(600万円 + 200万円)× 23% ー 636,000円 = 1,204,000円となり、年末調整などで既に支払っている税金との差額が発生します。
1,204,000円 - 772,500円 = 431,500円つまり、差額の431,500円を確定申告で納めることになります。
仮想通貨の利益の計算方法
仮想通貨で利益を得た場合の計算方法についてさらに具体的に解説します。
仮想通貨間の取引
移動平均法と総平均法
仮想通貨取引の1年分の合計所得額を計算する方法は、「移動平均法」と「総平均法」の2種類があります。確定申告の際にはどちらかの方法を選択した上での申告が必要です。また最初の申告時に選択した計算方法は次年度も継続して使用しなくてはいけないため注意しましょう。
移動平均法とは仮想通貨の購入の度に購入額と残高を平均し取得価額を算出する方法です。一方で総平均法とは1年間の購入平均レートをもとに計算した購入金額合計と、売却金額合計の差額を算出する方法です。
同一の仮想通貨を複数取引したとき
仮想通貨取引の最中には同じ銘柄の仮想通貨を何度も売買したり、一部を売却したりすることがあるかもしれません。このように同一の仮想通貨を複数回にわたり取得する場合は移動平均法を利用して所得を計算します。
例えば1BTC=30万を3枚購入すると購入額は90万円です。1BTCが40万円になったので、1枚を追加で購入すると購入額合計は130万円です。その後1BTCが35万円に下がったので、2枚分を売却すると売却額合計は70万円となります。
それでは移動平均法を用いて上述の1BTCの取得金額を計算してみましょう。計算式は以下の通りです。
130万円(購入額合計)÷ 4枚(保有枚数)= 32.5万円
1BTC当たりの取得金額は32.5万円となります。次に所得金額を計算してみましょう。
70万円(売却額合計)- 32.5万円 × 2枚(売却枚数) = 5万円
以上の計算で5万円が所得金額となることがわかりました。今回は移動平均法を用いての計算方法をご紹介しましたが、国税庁のタックスアンサーでも原則として移動平均法を用いるよう記述されていますので、移動平均法のみ押さえておけば問題ありません。
仮想通貨の分岐によって新たなコインを取得したとき
仮想通貨の分岐によって新しいコインを入手した場合は無料で取得しているため、入手時点では市場価格は存在せず税金はかかりません。しかしコインの取得価格が0円のため、売却した場合は売却価格、商品購入の場合は商品購入額、他のアルトコインに交換した場合はアルトコイン購入額がそのまま所得金額となり、その分の税金がかかります。
税金計算に苦手意識がある方はこちらのサービス「Guardian」がおすすめです。
「Guardian」は仮想通貨の税金に関するアドバイスをもらえるだけでなく、「仮想通貨専門」の税理士に相談ができるという点で、他のサービスよりも優れていると思われます。
仮想通貨の税金に関する注意点
確定申告を行わなかった
仮想通貨は、匿名性が高い通貨ですが、税務署が仮想通貨取引所に調査に入れば、取引所は記録を提出しなければなりません。
また国際的にも「共通報告基準 (CRS:Common Reporting Standard) 」という仕組みが構築され、各国の税務担当局が情報交換できるようになっています。
仮想通貨の特徴に、匿名性が高いということ以外に「記録の改ざんが不可能」ということもあります。つまり取引記録は永遠に残ります。
脱税が発覚すると、500万円以下の罰金か5年以下の懲役が課せられる上に、さらに無申告加算税、重加算税、過少申告課税、延滞税などが上乗せされます。
仮想通貨は損益通算・繰越控除ができない
仮想通貨の税制上のデメリットは損益通算ができず、繰越控除もできないことです。所得税の区分では仮想通貨は雑所得に当てはまります。雑所得では損失が出た場合に他の所得区分と損益を差し引きし申告することができません。
要するに仮想通貨で損失、株や不動産で利益が出ていた場合に仮想通貨の損失分を相殺することができないということです。ただし仮想通貨同士の損益や同じ雑所得内の損益は相殺することができます。
また仮想通貨の所得区分である雑所得では譲渡損失の繰越控除も利用できません。譲渡損失の繰越控除とは、譲渡益と差し引きしそれ以上に損失が上回る場合に3年間損失が繰越可能で、後の利益と相殺や節税のできる制度です。
仮想通貨の節税対策
制度上認められている節税は以下の通りです。
法人化
個人で仮想通貨を運用する場合は所得を得れば得るほど税率は高くなる累進課税制度の総合課税が適用されます。そのため最高税率は所得税と住民税を合わせると約55%に及びます。しかし法人化することで税率を大幅に下げることが可能であり、運用する金額によっては効果的な節税ができるかもしれません。
法人の実効税率は利益が800万円までは約15%、800万円超でも約23%です。そのため最高実効税率は法人住民税を合わせても約33~35%程度です。個人の所得税の55%とは比較にならないほど下がります。
また雑所得ではできなかった損益通算が法人の場合は可能です。万が一に赤字が出てしまっても、翌年の利益と相殺することができます。さらに法人では経費の対象となる範囲が拡がるため、減価償却や細かい費用を計上することが許されるなど、さまざまな節税方法があることもメリットといえるでしょう。
個人事業主として登録
法人化するほどの利益が出ていなくても、個人事業主として登録し、事業として仮想通貨取引を行えば、税制上の優遇措置を受けられます。確定申告の方法に「青色申告」を選択すれば、様々な税制上の優遇措置を受けられます。
青色申告は「複式簿記」という方法で収支記録を付ける必要がありますが、会計ソフトなどの利用で簡単にできます。複式簿記が必要で毎年の確定申告も必須になりますが、最大65万円の控除が適用されたり、赤字を3年間繰り越せるといったメリットがあります。
経費
仮想通貨取引に関する経費は、必要経費として利益から差し引くことができます。例えばマイニング専用機としてパソコンを購入した場合や取引記録を記録するための文具を購入した場合、また仮想通貨に関する書籍を購入したりセミナーに参加したりした費用も、経費になります。
自宅で取り引きしている場合、仮想通貨取引に使用した電気代を必要経費にすることもできます。パソコンの使用時間やコンセントの数から論理的に矛盾がないように電気代を計算し、それを経費とすることもできます。
ただし、いずれの場合も税務署を納得させられるだけの理由や根拠が必要です。レシートや領収証など、関係するものは全て保管しておきましょう。
損失を確定させる
1年が終わりに近づき、既に多くの利益が確保できて確定申告が必須の状況のとき、含み損を抱えた通貨があれば、その年のうちに損失を確定させるというのも一つの方法です。
損切りを考えている通貨は年内に損失を確定させ、利益を小さくすることで納税額を抑えることができます。
まとめ
本記事では、仮想通貨取引で発生した利益にかかる税金や税金の計算方法および節税の方法を紹介しました。仮想通貨に関する法整備は徐々に進んでおり、今後税金についても制度が大きく変更する可能性があります。
納税について不安なことがある場合は、税務署や税理士といった専門家に相談し、独断で判断しないよう注意しましょう。