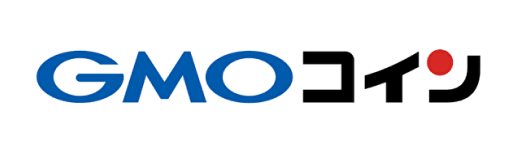- 日本において仮想通貨が認められ、規制を受けることになった
- 世界各国で法整備が進められている
- 金融庁が仮想通貨取引所の検査を厳しく行っている
仮想通貨の市場が大きくなるにつれ、世界各国で法規制が進んでいます。規制により価格が大きく変動することもあるため、取引をする際には各国の規制状況を把握することが大切です。
今回は、日本での規制状況と、世界各国の規制方針をみていきましょう。
現在の日本の仮想通貨規制はどうなの?
改正資金決済法
2017年4月1日に施行された「改正資金決済法」は、仮想通貨に関する初めての法律です。改正資金決済法の中で、仮想通貨に関する部分のみを「仮想通貨法」と呼ぶこともあります。
この法律によって、日本における仮想通貨の存在は、公に認められることとなりました。それと同時に、国による規制を受けることにもなりました。
仮想通貨の売買を行う業者は、「仮想通貨交換業者」として登録が必要になりました。2017年10月1日に、金融庁は「仮想通貨交換業者」として16社を登録しました。申請された業者が全て登録されたわけではなく、16社以外は継続審査となりました。
それ以降新たに登録された業者はありませんが、継続審査中の業者は、2018年5月7日現在は「みなし業者」として営業可能です。
日本の仮想通貨
日本が仮想通貨を認めたということは、世界に大きなインパクトを与えました。それまで何の後ろ盾もなかった仮想通貨が、日本という国に認められる存在になったからです。
仮想通貨界における日本の市場は俄然注目を集め、取り引きも活発に行われるようになりました。
2018年1月の巨額流出事件
2017年後半は仮想通貨界全体が盛り上がり、ビットコインを始めとする通貨の価値が一気に高まりました。
そんな中、日本の仮想通貨取引所を舞台としたネム(XEM)の巨額流出事件が発生しました。当時のレートで約580億円分のネムが、不正に送金されてしまいました。
テレビや新聞のニュースでも大きく取り上げられ、仮想通貨に興味の無かった人達にも知られるほど大きな事件として報道されました。
舞台となった取引所は、登録審査中の「みなし業者」で、セキュリティの甘さを突かれたものでした。
金融庁の立入検査
ネムの巨額流出事件を受け、金融庁は取引所への緊急の立入検査を実施しました。既に「仮想通貨交換業者」として登録済みの業者も対象となり、主にリスク管理体制を検査したと見られています。
立入検査は複数回に及び、業務停止命令や業務改善命令など、厳しい処分を受ける業者もありました。また、仮想通貨交換業者への登録申請を断念し、取り下げる業者も現れました。
自主規制
金融庁の厳しい姿勢を受け、業界での自主規制も進められています。仮想通貨交換業者・全16社が参加し、「日本仮想通貨交換業協会」が設立されました。みなし業者やこれから参入する業者へも参加も呼び掛け、業界の健全な発展を目指しています。
海外の仮想通貨規制はどうなの?
仮想通貨は、もはや無視できない存在にまで成長しました。日本は仮想通貨を好意的に捉えていますが、国ごとに仮想通貨の位置づけは様々です。
アメリカ
これまでは「送金業者」として州ごとに規制されていましたが、米国証券取引委員会(SEC)による全国的な規制が進められています。仮想通貨取引所は、「証券取引所」としてSECに登録することが必要になります。
アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)は、仮想通貨を通貨というより「資産」として方向づけ、税金に関する見方も明確にしました。
中国
中国では5万ドルを超える外貨の購入は認められていません。中国の富裕層は規制の対象外だった仮想通貨に目を付け、その資産を海外投資に向けました。「一帯一路」政策を推し進める中国にとって、仮想通貨による資金の海外流出は大きな問題でした。
そのため、中国当局は仮想通貨の取り引きやマイニングの規制に乗り出しました。一時はビットコイン取引の9割以上が中国に集中していましたが、今は仮想通貨に関することは規制の対象となっています。
ただし、香港においては特に制限はなく、Binance(バイナンス)やHuobi(フオビ)といった取引所があります。
韓国
韓国の仮想通貨熱は熱狂的で、2017年12月の仮想通貨全体の高騰を牽引していました。しかし2018年1月に法務省から仮想通貨取引禁止法案が発表され、仮想通貨の下落の要因となりました。
その後、この報道に反対する多くの請願書が青瓦台(韓国大統領官邸)に提出され、政府はこの法案を支持しておらず、短期的には仮想通貨を規制しないという結論を下しました。
ただし、仮想通貨の健全な取り引きに向けての法整備は進められており、口座開設の際の本人確認などが厳しく行われています。
ジンバブエ
長期に渡るハイパーインフレーションによって自国の法定通貨が意味をなさないジンバブエでは、ボーダレスな価値を持つ仮想通貨は魅力的です。仮想通貨Dash(DASH)は、ジンバブエの公式デジタル通貨を目指しています。
銀行口座所有率よりスマホ所有率が高い国において、仮想通貨は使いやすく現実的な決済手段として期待されています。
ベネズエラ
これまで外貨獲得は石油産業に頼ってきましたが、石油産出量は減少しておりインフレが懸念されています。外貨の枯渇が想定される中、資源がなくても外貨獲得につながる仮想通貨のマイニングが脚光を浴びています。
また、ベネズエラ政府は独自トークン「ペトロ」の発行も計画しています。しかし、ベネズエラに対し経済制裁中のアメリカが、ペトロを購入した投資家にペナルティを課すとしており、今後の動向が注目されています。
今後日本で規制は強化されるの?
仮想通貨取引所
2018年1月の巨額流出事件を受け、金融庁は仮想通貨取引所の検査を厳しく行っています。これまで特に規制がなく、取引所としての信頼性が分かりにくい状況でしたが、「仮想通貨交換業者」として登録されることが、一定の信頼性を担保することになります。
取引所の淘汰が行われ、ユーザーにとって信頼できる取引所だけが生き残ることになります。
KYC(Know Your Customer:顧客確認)
これまで取引所ごとに定められていた口座開設手続きは、金融機関の口座開設時と同程度の本人確認(KYC)が求められるようになります。(取引所によっては、これまでも行われていました。)
匿名性が高く、マネーロンダリングや脱税などの犯罪への利用が懸念される仮想通貨ですが、KYCの徹底によって健全な取り引きを目指します。
2018年3月 G20財務大臣・中央銀行総裁会議
アルゼンチンで開かれたG20会議では、急速に普及が進む仮想通貨への対応を協議する場としても注目されました。日本をはじめ、仮想通貨に大きな影響を持つアメリカ、中国、韓国もメンバーに入っています。
以下の点などが、話し合われました。
- 資産としては有効だが、通貨としては不完全
- 禁止しないが規制は必要
- 犯罪防止対策やKYC(Know Your Customer:顧客確認)の徹底が必要
- 7月のG20会議で規制についての提案を行う
まとめ
仮想通貨は爆発的に普及していますが、規制に向けた取り組みは始まったばかりです。今後は各国と連携しつつ、排除のための規制ではなく、健全な取り引きを行うための規制が進められていくと思われます。