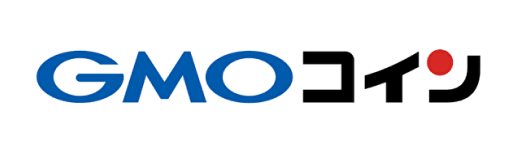- DeFiとは分散型金融を指し、ブロックチェーン技術を活用した非中央管理な金融サービスを提供
- DeFiはイーサリアムブロックチェーンを基盤とし、スマートコントラクトを通じて行われる
- DeFiと従来の金融サービスの違いは主に4つ
- 米連邦準備制度理事会によるとDeFiは決済層、資産層、プロトコル層、アプリケーション層、アグリゲーション層の5つのレイヤーに分解される
- DeFiは2017年ごろに誕生し、2020年にバブルを迎える
- DeFiには構成可能性といったリスクもある
DeFiとは
DeFiとはDecentralized Financeの略称で「分散型金融」と呼ばれます。DeFiはブロックチェーン技術を活用するため、中央の管理システムを必要としません。
銀行や証券、仮想通貨取引所などの金融サービスをブロックチェーンを活用して提供するシステムのことをDeFi (分散型金融) と呼びます。
DeFiとイーサリアム (ETH)
DeFiはイーサリアム (ETH) のブロックチェーンを基盤に構築されています。DeFiのサービスはトークン化された仮想通貨を用いて提供され、取引はブロックチェーン上でスマートコントラクトを通じて行われます。スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で契約を自動的に実行する仕組みのことをいいます。
従来のブロックチェーン技術では資産の移動と管理がメインでしたが、DeFiでは金融資産の複雑な移動や取引が可能です。そのため取引に金融機関を利用する必要がなく、スピーディな金融資産取引が可能です。
DeFiと従来の金融サービスとの違い
従来の金融サービスとDeFiの違いは以下の通りです。
- 中央管理システムによる監視の不在
- 居住地に関係なく利用可能
- 透明性が高い
- 構成可能性
DeFiと従来の金融サービスの違いの1つ目は、中央管理システムによる管理や監視がいらないことです。
従来の銀行などの金融サービスは運営元が存在し、運営組織への信頼で成り立っていました。一方でDeFiでは、ブロックチェーンが基盤となります。そのためDeFiは中央集権的な組織の影響を受けず、人間ではなくスマートコントラクトが内容を処理します。
DeFiと従来の金融サービスの違いの2つ目は、居住地に関係なく利用できることです。
従来の金融サービスと異なり、DeFiは銀行や国家などの組織に依存していないため、世界中のどこからでも、インターネット環境が整っていれば恩恵を受けられます。
DeFiと従来の金融サービスの違いの3つ目は、透明性の高さです。
DeFiの基盤であるパブリックブロックチェーンでは、全てのトランザクション (取引) が公開されています。またDeFiのプロダクトでは取引以外にも、誰でもスマートコントラクトのコードが確認できるようになっています。
DeFiと従来の金融サービスの違いの4つ目は、構成可能性 (コンポーザビリティ) です。
構成可能性とは、あるシステムの各構成要素同士が互いに連携して機能することを指します。DeFiではプロダクトのスマートコントラクト同士を簡単に統合できるため、単体のプロダクトでは生み出せないような多様な機能をもったプロダクトを提供できます。
また既に存在するプロダクトのスマートコントラクトを統合することで、新しいプロダクトを開発する際の工数やコストを削減して効率化することにも期待できます。
DeFiの特徴
DeFiの大きな特徴は、主に以下の2つです。
- 個人が資産の管理権を持つ
- 特定の人間や組織に依存しない
DeFiの特徴の1つ目は、各個人が自身の資産の管理権を所有することです。
自身で資産に関するプライバシーの保護ができるため、第三者機関のセキュリティについて心配する必要がなくなります。一方で、トラブルが起きた場合には自身で責任を負う必要があります。
DeFiの特徴の2つ目は、特定の人間や組織に依存しないことです。
DeFiのプロダクトは管理組織が必要な従来の金融サービスとは異なり、すべてスマートコントラクトによって処理されています。
DeFiの構成要素
DeFiの主要な構成要素について、米連邦準備制度理事会 (FRB) が調査した内容を米連邦準備制度理事会のレイヤー構造に分解して説明しています。
- 決済層
- 資産層
- プロトコル層
- アプリケーション層
- アグリゲーション層
決済層とは、資産の所有権を保証し決済とコントラクトの実行を担う層です。ブロックチェーンとネイティブアセットによって構成されています。ネイティブアセットに該当するものとしては、ビットコイン (BTC) やイーサリアム (ETH) などが挙げられます。
資産層には、ネイティブアセットとトークンが含まれています。資産層は決済層で発行される全ての資産で構成されています。
プロトコル層は分散型取引所 (DEX) やレンディング、デリバティブなどの特定の活用事例のために整備されており、通常はスマートコントラクトによって制御されます。プロトコル層の各規格には、相互互換性の特徴があります。
アプリケーション層とは、プロトコルに接続するための窓口のことです。通常はWebブラウザによってアクセスされます。
アグリゲーション層は、アプリケーション層の延長線上に存在して複数のアプリケーションやプロトコルをまとめて管理する役割があります。異なるアプリケーションやプロトコルに同時接続することで、より最適なサービスを提供できるようになります。
DeFiの歴史
DeFiの最初のプロダクトは、2017年頃に誕生した仮想通貨の分散型取引所 (DEX) であると言われています。その後2018年から2019年にかけてDeFiの技術が進み、仮想通貨の貸し借りができるCompoundやヘッジファンドのBetokenなど、多様な機能をもったプロトコルが次々とローンチされました。2020年にDeFiはイールドファーミングの流行などの影響を受けてバブルを迎えたと考えられています。
DeFiは誕生からの歴史が浅く、発展途上のため課題も見受けられますが、今後も市場の拡大と技術の進歩が予想されています。
DeFiの現状課題
現状のDeFiにおいて、指摘されている主な課題は以下の通りです。
- 構成可能性のリスク
- 法的な課題
- スケーラビリティ問題
DeFiの現状の課題の1つ目は、構成可能性に関連するリスクです。
DeFiは構造上、どこかの層でトラブルが起きた場合はその層の上に構築されている全ての層が影響を受けてしまいます。DeFiの構成可能性のリスクは、スマートコントラクトで同時接続されているからこそ発生する課題です。
DeFiの現状の課題の2つ目は、法的な問題です。
DeFiでは責任の所在が明らかになっていないため、現状では全ての取引の責任をユーザー自身が負う必要があります。そのためDeFiに関連した詐欺事件も発生しているため、注意が必要です。
DeFiの現状の課題の3つ目は、スケーラビリティ問題です。
スケーラビリティ問題とは、ブロックチェーン技術に関する障害のことです。スケーラビリティ問題は、1つのブロックチェーン内に書き込める取引データ数が限られていることによって発生し、処理速度の低下と送金遅延を引き起こしてしまいます。
以上の問題のほかにも、UIや操作性なども課題として挙げられています。
DeFiのまとめ
DeFiには従来の金融サービスと比較して課題もあげられますが、DeFiの領域は今後も成長が見込まれています。
今の段階でDeFiの基礎についてしっかりと理解して、仮想通貨の取引を行いましょう。