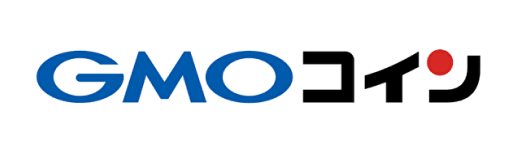仮想通貨詐欺とは
2017年にビットコイン (BTC) が20倍以上高騰し「億り人」と呼ばれる人が多数出現しました。この影響もあり、仮想通貨に投資をすれば多額の利益が得られると考えている人も多いのではないでしょうか。
仮想通貨の詐欺は、このような人たちの心理を利用して「必ず利益が出せる」などと謳い、大金を支払わせるものです。どんな投資でも必ず利益が出せるという確証はありません。甘い誘惑には注意してください。
仮想通貨詐欺の種類
仮想通貨詐欺の主な種類は以下の4つです。
- マルチ商法
- ICO
- ウォレットアプリ
- 振り込め詐欺
1つめは、口コミなどによって販路を広げていく、ネットワークビジネスを利用した詐欺方法、いわゆるマルチ商法です。
具体的には、用意されたマニュアル通りに実行すればより多くの人数を勧誘でき、勧誘した人数に応じて配当が受け取れるといった内容です。どの詐欺会社も自社は業績がよく安定していると嘘をついているので、信じてはいけません。
2つめは、ICOを利用した詐欺です。
ICOとはInitial Coin Offering(イニシャル・コイン・オファリング)の略称で、企業やプロジェクトチームが独自の仮想通貨を発行して販売する資金調達方法です。ICOを利用した詐欺では独自に発行した通貨を購入してもらい、ある程度の資金を集めたら、約束していた事業を起こさず資金をそのまま持ち逃げする手口です。
ICO自体はメジャーな資金調達方法で、多くの企業やプロジェクトチームがICOによって資金を調達していますが、中には資金だけを目的としたものも存在します。投資する際には企業の事業計画書や開発チームに目を通し、将来性が期待できるか客観的な情報をもとに判断しましょう。
3つめは、ウォレットアプリを利用した詐欺です。
ユーザーがアプリ記載のアドレスに仮想通貨を送金すると、そのまま通貨が返ってこないという事例があります。ウォレットアプリをダウンロードする際は、アプリ情報やユーザー数を確かめ、公式のアプリであるか必ずチェックしましょう。
4つめは、振り込め詐欺です。
具体的な事例としては「国際ロマンス詐欺」などがあります。マッチングアプリでやり取りしている標的者に対して、結婚資金や新居の費用という名目で儲かる投資をしようと持ちかけ、運用して儲かっているように見せかけて、どんどん資金を振り込ませます。
中には被害額が1,000万円を超える事件もありました。資産運用の世界で必ず儲かるという話は絶対にありえません。怪しいなと感じたら金融庁や消費者庁に相談しましょう。
過去の詐欺事件
ICOを利用した詐欺事件を2つ紹介します。
1つめは、ワンコインです。
ワンコインは、ブルガリア共和国にある企業が行っていたプロジェクトで、瞬時の送金システムを構築し、金融業界に革命を起こすと謳っていました。
ワンコインは、ネットワークビジネスの販売形式をとっていて、ワンコインを知人に紹介することで手数料をもらえる仕組みになっていました。紹介すればするほど報酬がもらえると謳っていましたが、実際は上層部だけが儲かる仕組みになっていたため、世界各国でワンコインに関わる人が逮捕されました。
2つめは、Modern Tech社のピンコインとアイファンです。
ベトナム・ホーチミン市に所在を置くModern Tech社は、ピンコインとアイファンを使ったICOを行い「月利48%以上」「4ヶ月以内に払い戻し」「出資者の紹介で8%のキックバック」といった文言を掲げ、約3万2000人から総額約710億円もの資金を集めていました。しかし、その後大規模な詐欺案件であったと報じられ、プロジェクトも頓挫しています。
詐欺に遭わないために
では、詐欺かどうかを見抜くにはどのような点を見ればよいのでしょうか。
多くの詐欺案件では、購入履歴が残らないように取引所を介さずに仮想通貨を購入させようとします。購入履歴が残ってしまうと後から被害額を請求されたり、送信先からアドレスを特定されたりといったリスクがあるためです。そのため、通貨の購入方法が不自然な場合は詐欺の可能性を疑いましょう。
また金融商品取引法では価格を保証する行為を禁止しているため、元本保証や価格保証を謳っているところも詐欺と考えて間違いないでしょう。仮想通貨は価格変動が大きいため、元本保証や価格保証を100%実現できるのはありません。
SNSで不特定多数の人を勧誘するケースも詐欺の可能性があります。本当に利益が出せるのであれば、わざわざ知らない人を勧誘する理由がないからです。SNSでは氏名や経歴を偽造できるので、信頼できそうな人であったとしても関わってはいけません。
有名人、有名企業を広告にしている場合も安易に信用してはいけません。詐欺まがいの案件でも、権威付けをするために有名人や有名企業を広告に用いることが多々あります。
これらの点を踏まえて自分で情報を集め、正確な判断を心がけましょう。
詐欺に遭わないためには、金融庁が発信する暗号資産に関する注意に目を通し、事例や実態を理解することが大切です。
また実際に取引を行う際には信頼できる取引所で取引を行いましょう。SNSや周囲の声に惑わされることなく、自分自身できちんと情報を調べ、信頼できるものなのかを判断しましょう。
それでも未然に防ぐことができないこともあると思います。少しでも不安に思うことがある場合や詐欺に遭ってしまった場合はすぐに相談窓口に問い合わせをしましょう。
詐欺に遭った時の相談窓口
仮想通貨に関する相談窓口は以下のとおりです。
金融庁 金融サービス利用者相談室
営業時間:平日10時~17時
電話番号:0570-016811 (IP電話からは03-5251-6811)
FAX:03-3506-6699
インターネット:https://www.fsa.go.jp/opinion/
独立行政法人 国民生活センター 消費者ホットライン
営業時間:平日10時〜12時/13時〜16時
電話番号:188
仮想通貨詐欺まとめ
仮想通貨詐欺にはマルチ商法、詐欺コインを使ったICOの悪用、偽のウォレットアプリなどのさまざまな手口があります。
過剰な紹介キャンペーンを行っていたり、元本保証や価格保証をしていたりする場合は詐欺の可能性を疑ってください。
仮想通貨に限らず、資産運用の世界で「絶対」はありません。都合のいい情報を鵜呑みにせず、客観的な視点から判断する姿勢を心がけましょう。
もし詐欺にあってしまったかもと思ったら、金融庁や国民生活センターの相談窓口に相談しましょう。