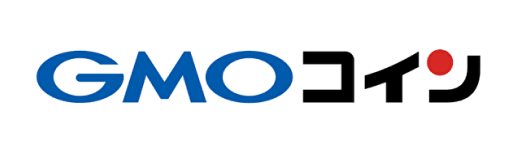- 逆指値の特徴やメリットを押さえてトレードに役立てる
- さまざまな注文方法の特徴もおさらいして違いを知る
- 逆指値の使い方を覚えて実際に利用する
逆指値注文は指値注文の一種で主にリスクケアのために使われることが多いです。使える場面の幅が広いので使いこなせるようになればトレードの質が格段に上がります。逆指値注文の仕組みと使いどころを見てみましょう。
逆指値とは
逆指値の基本情報
逆指値とは、ある銘柄の価格が自分があらかじめ設定した価格(参照価格)以上またはそれ以下になった場合に自動的に注文を実行する方法です。
ただし通常の指値とは異なり、買いの場合には「指定した価格まで上昇したら買い」となり売りの場合には「指定した価格まで下落したら売り」といった注文になります。
逆指値を利用することで、リスクを上手くコントロールすることができます。そして価格の上昇トレンドに転じるタイミングで、買い注文を自動的に出せるメリットがあります。
基本的な注文方法のおさらい
| 指値注文 | 指定した価格に達するとポジションを保有することができる注文方法 |
| 成行注文 | すぐにポジションを保有することができる注文方法 |
| 逆指値注文 | 指定した価格以上で買い、もしくは以下で売る注文方法 |
指値注文
指値注文とは、指定した価格に達することでポジションを自動的に保有することができる注文方法です。
成行注文
成行注文とは、注文時点ですぐ約定する価格帯で注文する方法です。
逆指値注文の種類
逆指値にはいくつか注文の種類があるので解説します。特徴を押さえて上手く利用しましょう。
IFD注文
IFD注文とは、「新規注文」と「決済注文」を同時に発注することができる注文方法です。新規の注文が約定したときに、決済注文も自動的に有効となります。
OCO注文
2種類の注文を同時に出して、一方の注文が成立すると片方の注文が自動的に取り消しになる注文方法です。
少し例を挙げてみます。
自分の保有している銘柄の価格が1000円だとします。この時に通常の指値注文の価格を1100円とすると同時に、価格が950円まで下がったら自動的に損切りするような注文も出せるということです。
逆指値を使うメリット
メリット1 損切りに役立つ
価格が1080000円のときに買い注文を発注したとします。その後相場が転換したときに備えて、1070000円で売りにする逆指値を設定します。
1080000円で買い注文を出しているので、もし価格が急落しても損失を10000円に押さえることができます。
メリット2 常にチャートを見れないときに役立つ
逆指値を設定しておくことで、自動的に注文を発注・決済してくれます。そのためチャートを常に見ることができない環境でも取引することができます。
メリット3 トレンドを逃がさずに利益を狙える
逆指値しておくことでトレンド転換を逃さず、有利に取引することができます。経済指標やテクニカル分析を駆使して、逆指値を上手く利用しましょう。
逆指値のデメリット
デメリット1 なかなか注文ができない場合がある
逆指値のデメリットですが、相場の動き次第では注文できない場合があるという点です。
自分の予想よりも価格が変動しなかった場合は、もちろん注文はできません。
デメリット2 損切りが早くなってしまう場合がある
もう一つのデメリットは、損切りが早くなってしまうと、そのあとに価格が上昇してしまう可能性を捨ててしまうということです。
損切り直後に価格が回復してしまうというのは、トレード上級者でも起きることがあります。もちろん、さらに価格が下がって損害が増大してしまうリスクからは逃れることができるという点では、それほど大きなデメリットとは言えませんが、逆指値は儲かる可能性も捨ててしまうことも念頭に入れておきましょう。
逆指値の使い方
逆指値注文がどのような注文かこれまで見てきました。次は実戦チャートの中での有効な使い方を見てみましょう。
損失限定売り
逆指値注文の最も基本的な使い方です。自分にとって不利な方向に相場が動いたときのリスクを限定する目的があります。
買いポジションを保有しているときの「売り逆指値」
- 上のチャートでは1200円を超えたところから相場が底堅くなってきたので1250円で買いポジションを建てています。
- 思うような上昇トレンドが発生せず、もみ合いのレンジ相場になってきたので1180円で売りの逆指値注文を入れています。
- そのまま下落してしまい1180円に達した時点で売りの逆指値注文が実行され、80円の損失が確定しました。しかしこの後も下落は続いているので、効果的な損切りだったと言えます。
売りポジションを保有しているときの「買い逆指値」
- 価格が1200円を下回ったところから上値が重くなってきたので1160円で売りポジションを建てています。
- 相場が上昇する気配を示してきたので、このまま上昇してしまった時の損失を限定するために1250円で買いの逆指値注文を出しています。
- そのまま相場は上昇し1250円で売りの逆指値注文が実行され、90円の損失が確定しています。こちらもこの後に強い上昇が起こっているので効果的な損切りだったと言えます。
このように逆指値注文は予想と反した方向に相場が動き始めた時に使うと、損失を限定して最悪の事態を避けることができます。
損失限定条件付き利食い狙い
こちらも基本的な逆指値注文の使い方です。指値注文を出しておく一方で、相場が不利な方向に動いたときに損切りが執行されるよう逆指値注文を発注する方法です。
- 1200円を上回ったところから底堅い状況になってきたので1220円で買いポジションを建てました。
- レンジ相場のもみ合いが続く中で、1310円に達したら利益確定の指値注文を出す一方で相場が急落したときのリスクケアとして1180円で逆指値注文を出しました。
- このまま相場が上昇したときには1310円で売り指値が執行され90円の利益が確定し、もし下落してしまっても1180円で売り逆指値が執行され40円の損失に抑えられます。
この方法では利益確定と損切りのどちらにも対応できるので、相場の方向感が見えないときやチャートを見れる時間がない時に効果的です。
利益確定売り
既に含み益が発生しているときに、反対の方向に相場が動いたらそこで利益を確定させてしまうための逆指値注文です。
- 相場の上昇トレンドが見えたところで1160円で買いポジションを建てました。
- 一旦は下落したもののその後上昇を続け、1360円まで達しました。まだ上昇する勢いはあるものの、相場が反転したときのリスクケアとして1320円で売りの逆指値注文を出しておきます。
- その後相場は下落し、1320円で売り注文が執行されて160円の利益が確定しました。この後さらに下落が続いているのでこのタイミングでの利益確定はとても効果的だったと言えます。
このように現時点での含み益を失いたくないときにも逆指値注文は有効です。
トレンドフォローの買い
相場が強いトレンドに乗った時に、それに合わせて逆指値注文の価格を更新していく方法です。
- 1200円の手前で強い上昇が見られたため、さらなる上昇を狙って1170円で買いポジションを建てました。
- 同時に反転して下落した場合に備えて1070円で逆指値注文を出しておきます。
- 逆指値価格の1070円まで下がることなく1240円まで上昇しました。これを見て売り逆指値を1190円に訂正し、20円の利益を確保しました。
- 相場はさらに上昇を続けて1360円まで達したところで、再び逆指値を1340円に訂正し170円の利益を確保しました。
- 後に相場は反転し、1340円で売り逆指値が実行されて170円の利益が確定しました。
この方法ではリスクを限定しつつ相場が有利な方向に動いたときには利益を最大限に伸ばすことができるので、強いトレンドが発生しているときにとても有効です。
レンジ抜けの買い・売り
相場がレンジ相場から抜けたタイミングで自動的に新規ポジションを建てることで、その後のトレンドに乗った利益を狙う方法です。
- 相場は1150円から1250円のボックス圏にあります。このボックス圏を上抜けしてさらなる上昇が期待できそうなので、1240円に達しレンジの天井が見えたところで1270円で買いの逆指値注文を出しておきます。
- すぐにレンジ相場を上抜けし、1270円で新規買いポジションを建てることができました。- 実際にこの後には上昇トレンドが発生しているので大きな利益が期待できます。
このように逆指値注文は新規ポジションを建てるときにも使えます。レンジ相場を抜けるポイントを見計らって注文を出せればその後の大きな利益が期待できます。
逆指値を使う際に気を付けたいこと
約定と価格の差から生じる損失
逆指値では、注文した時点の価格と実際に約定された価格の差が発生します。この価格差をスリッページといいます。
スリッページは相場の急な価格変動によって発生します。
チャートが注文価格に到達しないと売買されない
逆指値注文は、チャート上で対象銘柄の価格が設定金額に到達しないと注文が通りません。
まとめ
逆指値はリスクコントロールすることができる注文方法です。
万が一設定した金額に価格が達しない場合は、逆指値の注文が通ることはありません。さまざまなテクニカル分析や経済指標などを駆使して、適切な逆指値を設定しましょう。